「捕まえないといかんのだ!」ホームズは歯ぎしりをしながら言った。「くべろ、給炭夫!全速力をだせ!船を燃やせば追いつくはずだ!」
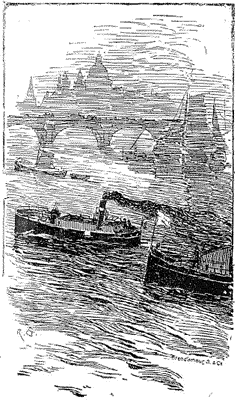
警察艇は必死でオーロラ号を追いかけた。燃焼炉はゴーゴーとうなり、強力なエンジンは、シューシュー、チンチンと巨大な金属製の心臓のような音を立てた。鋭い角度の船首が静かな川面を切り裂き、二つのうねる波を船の左右へと送り出していた。エンジンが脈動する度に、船は生き物のように飛び跳ね、振動した。船首にある大きな黄色のランタンが、瞬きながら長い光をじょうごのように船の前に投げかけた。目の前の海面に浮かぶぼんやりした黒い影が、オーロラ号の場所を示し、船尾の白い泡の渦が、船が疾走する速さを物語っていた。警察艇は、はしけ、蒸気船、商船、それぞれ一隻づつ、後ろについたり回り込んだりしながら縫うように進んだ。暗闇から怒号が浴びせられた。しかしそれでもオーロラ号は轟音を立てて進み、警察艇はピッタリとその後を追った。
「くべろ。おい、くべるんだ!」ホームズは機関室を覗き込みながら叫んだ。鷲のような必死な顔を下から荒々しい輝きが照らしていた。「ありったけの蒸気を出せ」
「ちょっと差が縮まったようだ」オーロラ号を見つめながらジョーンズが言った。
「間違いない」私は言った。「まもなく追いつくぞ」
しかしその瞬間、運悪く、三艘のハシケを引いたタグボートが間に迷い込んだ。舵を激しく下手に切って、やっと警察艇は衝突を避けた。だが、回りこんで元の航路に戻る前に、オーロラ号はたっぷり200ヤードの距離を稼いでいた。しかし船の姿を見失ってはいなかった。そしてうす暗くぼんやりした夕暮れは、今やくっきりと星の出た夜空に変わろうとしていた。こちらの船のボイラーは極限まで働かされ、脆い外壁は船を推進させている恐ろしいエネルギーでブルブル震えて、きしんだ。船は淀みを突っ切り、ウェスト・インディア・ドックを通り、長いデットフォード・リーチを下り、そして再びアイル・オブ・ドッグを回って後を追った。目の前のぼんやりした滲みは、今や、はっきりと優美なオーロラ号の姿に変わった。ジョーンズがサーチライトを船の方に回したので、デッキ上の人影を鮮明に見ることが出来た。一人の男が船尾の横に座っていた。何か黒い物体を膝の間に置き、その上に前かがみになっていた。その隣に黒い固まりが置かれており、ニューファンドランド犬のように見えた。舵をとっていたのは少年で、燃焼室の赤い輝きを背景に、父親のスミスが上半身裸になり、必死で石炭をくべている姿が見えた。彼らは最初、この船が本当に自分たちを追跡しているのかどうか、ちょっと疑っていたかもしれない。しかし、曲がりくねった航路をどこまでも追いかけて来たので、もはや疑問の余地はなかった。グリーンウィッチで、警察艇はオーロラ号の後ろ300歩くらいになった。ブラックウォールで、250を切った。私は波乱に富んだ人生の中で、様々な国に行き、様々な獲物を追った。しかしどんな狩りでも、この狂ったようにテムズ川を駆け下って行く人間狩りほど激しいスリルを味わったことはなかった。一ヤードずつ確実に我々は彼らに迫っていた。夜の静けさの中で、オーロラ号のエンジンがガチャガチャいう音が聞こえてきた。船尾の男はまだデッキにかがんでおり、両手を忙しそうに動かしていた。時々、彼はこの船との距離を測ろうとするかのように、ちらっと目を上げた。船はぐんぐん接近した。ジョーンズが停船しろと叫んだ。我々の船は、オーロラ号の背後、四挺身もないところまで迫っていた。追う船も追われる船も、恐ろしい勢いで飛ぶように進んでいた。ここは、片側がバーキング・レベルで、反対側が陰気なパルムステッド湿地になっている川幅の広い区域だった。我々の呼びかけに、船尾の男が甲高いかすれた声で罵りながら、デッキから跳びあがり、両手を堅く握ってこちらに拳を振った。彼はかなり背の高い屈強な男だった。そして彼が両足を開いてバランスを取っている時、右足の腿の下に木の義足が見えた。彼が耳障りな怒りの叫びを上げた時、デッキの上に置いてあった丸めた荷物が動いた。それは真っ直ぐに伸び、小さな黒い人間になった、 ―― 私が見た中で最も背の低い人間だった ―― 、頭は大きく、不思議な形で、髪はもつれてぼさぼさだった。ホームズはすでに拳銃を抜いていた。私もこの凶暴な変形した人間を見て、急いで自分の拳銃を出した。彼は黒いアルスター外套か毛布のようなものを体に巻きつけており、外から見えたのは顔だけだったが、その顔だけで悪夢にうなされそうだった。獣性と残虐性がこれほど深く刻まれた顔はこれまで見たことがなかった。小さな目は、薄暗い光に輝き、燃え上がっていた。厚い唇は歯の後ろに反り返り、我々に対して獣のように怒り、歯を剥き出しにしてキーキーとうなり声を上げていた。
「あいつが手を上げたら撃て」ホームズは静かに言った。