六月の暖かい朝のことだった。末日聖徒達は、紋章に刻まれた巣に住む蜂のように忙しかった。勤勉な人間たちが奏でるにぎやかな音が、野にも、通りにも、満ち溢れていた。埃っぽい主要道路を通る、荷物をいっぱい積んだロバの長い隊列は、例外なく西部を目指していた。カリフォルニアで金鉱への熱狂が起き、選ばれし民の街を通って大陸横断ルートが敷設されたためである。辺境の牧草地からやってきた羊や子牛の群れや、果てしない旅に人馬共に疲れきった入植隊も、次々にその道を通った。こういう雑多な集団の間を、熟練の技を持った騎手を背にした一頭の馬が縫うように進んでいた。馬を駆け足で走らせていたのはルーシー・フェリアーだった。美しい顔は運動で火照り、栗色の長い髪は後ろになびいていた。彼女は父から街での仕事を依頼されていた。そして頼まれた仕事をきちんと終わらせたい一心で、それまで何度となくこなしてきた使いと同じように、まったく恐れを知らない若さで馬を飛ばしていた。旅に汚れた冒険者達は、驚いて彼女を見送った。毛皮の服を着て旅をする、表情を表に出さないインディアンでさえ、この色白の女性の美しさに驚嘆し、普段の平静さを崩した。
彼女は街の外れにまで到着していた。その時彼女は、荒っぽい風采の牧夫が六人がかりで引き連れている大きな牛の群れが道を塞いでいるのに気づいた。苛立った彼女は、隙間が開いたように見えた場所に馬を進めてこの障害物を通り抜けようとした。しかしほとんど前に進めないうちに、後ろからも牛が近づいてきて、荒々しい目をした角の長い牡牛の流れの中に完全に取り囲まれてしまった。彼女は牛を扱うのに慣れていたので、こんな状況になっても助けを呼ばず、色々なチャンスを巧みに活用して、馬を前に進め、行列を通り抜けようとした。偶然か故意か分からないが、不幸にも一頭の牛の角が馬の脇腹を激しく突き、馬は正気を失った。その瞬間、馬は怒りの鼻息荒く、後ろ足で立ち上がって飛び跳ねた。熟練の乗り手でなかったら投げ出されていたに違いない。絶体絶命の状況だった。興奮した馬が突っ込むたびに、また角にぶつかり、余計に狂乱する事になった。女性にできたことはただ、鞍に捕まっていることだけだった。もし滑り落ちれば、恐れおののいて制御不能になった動物の蹄に踏まれる恐ろしい死が待っていた。突然の非常事態に慣れていなかったので、彼女は頭がクラクラし、手綱を握る手が緩んだ。舞い上がる砂埃と、もがく馬の熱気で息が出来なくなってきた。もし、すぐ隣から優しい声が聞こえて、助けが来た事に気づいていなければ、彼女は絶望して奮闘するのを諦めていたかもしれなかった。その声と同時に、筋張った褐色の手が恐れおののく馬のくつわをつかみ、群れの中を無理やりに進ませて、まもなく牛の姿がまばらになる所まで彼女を連れて行った。
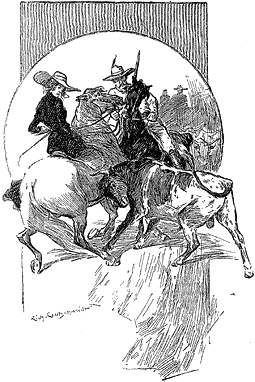
「怪我がなければいいが、お嬢さん」救助人は礼儀正しく言った。
彼女はその男の黒い精悍な顔を見上げ、元気よく笑った。「本当に怖かったわ」彼女は無邪気に言った。「ポンチョが牛の群れを怖がるなんて、誰が想像したでしょう?」
「鞍から落ちなくて、助かったな」男が真剣に言った。彼は背の高い粗野な感じの青年で、力強い葦毛の馬にまたがり、荒っぽい狩人の服に身を包み、長いライフル銃を背負っていた。「ジョン・フェリアーの娘さんと見たが」彼は言った。「その馬はお父さんの馬だろう。お父さんに会ったら、セントルイスのジェファーソン・ホープ一家を覚えているか聞いてみてくれ。もし俺の思っているフェリアーさんなら、俺の父と君のお父さんはすごく親しかったはずだ」
「家に来て自分で聞いたほうが良くない?」彼女は遠慮がちに尋ねた。
青年はこの提案が嬉しかったようで、黒い目が喜びに輝いた。「そうしよう」彼は言った。「山に二ヶ月も入っていたので、とても訪ねていける状態じゃない。ありのままの俺を見てもらうしかないな」
「お父さんはうんと感謝するわ。私もだけど」彼女は答えた。「お父さんはとても私を愛しているの。もしあの牛達に踏みつけられていたら、きっと立ち直れなかったでしょう」
「俺もだ」男が言った。
「あなたが!どちらにしてもあなたにはたいした問題じゃないと思うけど。あなたは私たちの知り合いでもないし」
この返答を聞いて、日に焼けた若い狩人が非常にしょげた顔をしたので、ルーシー・フェリアーは大声で笑いだした。
「冗談よ」彼女は言った。「もちろん、あなたはもう友達よ。ぜひ来てね。さあ急がなきゃ。お父さんが私を信用して仕事に使ってくれなくなるわ。さようなら」
「さようなら」彼はソンブレロを掲げて、彼女の小さな手にかがみ込んで答えた。彼女は馬を回して鞭をくれ、もうもうと砂埃を舞い上げて広い道を駆け出していった。