| 瀕死の探偵 1 | 瀕死の探偵 2 |
シャーロックホームズに部屋を貸していたハドソン夫人は我慢強い女性だった。絶えず奇妙な人物が、そしてしばしば不快な人物が、家の二階に押し掛けて来るばかりではなく、この一癖ある下宿人はちょっと極端な性格で、生活も不規則だったので、彼女は大変な忍耐が必要だったに違いない。とんでもない乱雑さ、妙な時間に音楽に夢中になること、部屋の中で時々拳銃の練習をすること、奇妙で、しばしば悪臭を放つ科学実験器具、そして彼を取り巻く暴力と危険の雰囲気、 ―― ロンドン中の借家人で、最悪の男だった。一方、彼の支払いは気前がよかった。私が彼と同居していた年月にホームズが部屋代として払った金で、間違いなく家が丸ごと買えただろう。
ハドソン夫人はどれほどホームズの行動が極端すぎるように思えても、彼に深い畏敬の念を抱き、決して邪魔をしようとはしなかった。ホームズの女性に対する態度は驚くほど優しく礼儀正しいものだったので、彼女はホームズを気に入っていた。彼は女性を毛嫌いして軽蔑していたが、常に礼儀正しい敵対者だったのだ。彼女が本気でホームズを尊敬している事が分かっていたので、結婚生活を始めてから二年目に彼女が私の部屋を訪れ、ホームズが衰弱してひどい有様になっていることを話しだした時、私はその話に聞き入った。
「ワトソン先生、ホームズさんは死にかけています」彼女は言った。「この三日間でどんどん衰弱しています。あと一日もつか分かりません。私に医者を呼びにやらせようとしないんです。今朝、私が会いに行くと、頬骨が突き出てぎらぎらした大きな目で私の方を見ていました。私はとうとう我慢できなくなり『ホームズさんの許可があろうとなかろうと、私は今すぐにお医者さんを呼びに行きますから』と言いました。『じゃ、ワトソンにしてくれ』ホームズさんはこう言いました。一刻も早く来てください。そうでないと、もう生きて会えないかもしれません」
私は彼の病気について何も聞いていなかったので衝撃を受けた。言うまでもなく私は急いでコートと帽子を身に着けた。一緒に馬車で戻るとき、私は詳しい事を尋ねた。
「私もあまり詳しくは知らないんです。ホームズさんは、ある事件の仕事で河近くのロザーハイス通りに行っていました。そこで病気をうつされて帰ってきたんです。水曜の午後に寝込んでからずっと寝たきりです。この三日間は食事も飲み物も喉を通りません」
「そんな!どうして医者を呼ばなかったんですか?」
「ホームズさんが呼ばせようとしなかったんです。あの人がどれほど有無を言わせないか、あなたならご存知でしょう。私はあの人の命令に敢えて歯向かうことは出来ませんでした。しかしホームズさんの命はもう長くありません。ちょっと見れば、すぐにご自分でもお分かりになるでしょう」
彼は実際、ひどい状態だった。11月の霧がかかって薄暗い気候だったので、病室は重苦しかった。しかし私の心にぞっとする恐怖をもたらしたのは、やつれてやせ衰えた顔がベッドから私を見ている事だった。彼の目は熱でぎらぎらし、頬は紅潮していた。そして黒いかさぶたが唇を覆っていた。ベッドカバーの上の細い手はひっきりなしに痙攣し、彼の声はしわがれて痙攣を起こしているようだった。私が部屋に入ったとき、彼はぐったりと横たわっていたが、私の姿を見ると、彼は私を見分けて目を輝かせた。
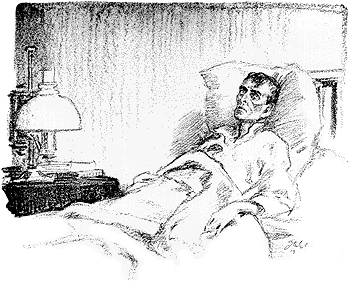
「やあ、ワトソン、厄日がめぐってきたようだ」彼はか弱い声で言った。しかしどこかに、かつての気楽な調子が残っていた。
| 瀕死の探偵 1 | 瀕死の探偵 2 |