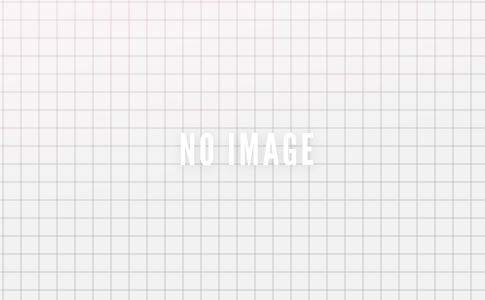「ストランド版 シルバー・ブレイズの冒険」は、初出誌ストランド・マガジンの体裁をそのままに、日本語化したもので、アマゾンで発売する「ストランド版 続シャーロック・ホームズ」に含まれる短編小説です。
ここでは、オンラインで書籍内容を確認できます。PDF版をダウンロードしてA4サイズにプリントすると、実際の書籍よりひとまわり大きくプリントされます。なお、PDFはイメージ形式で、実際の印刷よりもずっと画質の荒いものですので、ご了承ください。
ストランド版 シルバー・ブレイズの冒険[PDF版]
ストランド版 シルバー・ブレイズの冒険(0.1.0)
ストランド版 シルバー・ブレイズの冒険 [全文テキスト]
「やむをえん、ワトソン、行くしかない」ある朝、食事の席でホームズが言った。
「行く!どこへ?」
「ダートムーアのキングズ・パイランドだ」
意外ではなかった。実は、イギリス中の話題を独占する異常な事件に、彼がまだ関与していない方が不思議だった。ホームズは一日中、深くうなだれて、眉を寄せ、ひっきりなしに強烈な黒タバコをパイプに詰め、私の問いかけをいっさい無視したまま、部屋を歩き回り、最新版の新聞が配達されるたびに、ちょっと目を通しただけで投げ捨てた。たとえ無言でも、何が気になるか、私には手にとるようにわかっていた。新聞に載っていて、ホームズの分析能力が必要な事件は、ただひとつ、ウェセックス・カップ本命馬がこつぜんと姿を消すと同時に、その馬の調教師が惨殺された事件だ。だから、ホームズが突然その事件現場に行くと言い出しても、それは単に予期していたことが起きただけだった。
「ぜひ連れて行って欲しいが、足手まといか?」私は言った。
「ワトソン、来てくれるなら実に助かる。それに無駄足にはならないと思う。この事件には独特な点があるからな。パディントン発の列車に乗るなら、そろそろ出ないと間に合わない。事件については車内で詳しく説明しよう。君の高級双眼鏡を持って来てくれたらありがたい」
こうして1時間ほど後、私はエクセターに向かう一等車両に乗っていた。シャーロックホームズは、耳当てつき旅行帽をかぶり、気迫に満ちた鋭い顔で、パディントン駅で買い集めた新聞の最新版を夢中で読んでいた。ホームズが最後の1紙を座席の下に突っ込み、私にタバコ入れを差し出したのは、レディング駅をかなり過ぎた後だった。
「順調だな」ホームズは窓から外をながめ、ちらっと時計を見て言った。「今、時速86キロだ」
「400m標識は見えなかったが」私は言った。
「僕もさ。だが線路沿いの電柱は50m間隔で、計算は単純だ。それより、君もジョン・ストレイカー殺害とシルバー・ブレイズ失踪事件は、もう調べているだろう?」
「テレグラフとクロニクルは読んだ」
「この事件は、新たな証拠を発見するより、入手済みの証拠から確実なものを選別するのに、骨が折れるな。事件が奇妙で残虐なだけでなく、直接の利害関係者が山ほどいるので、憶測の話が多すぎて、もう大変なことになっている。記者や評論家の脚色を排除して、事実の骨格部分――否定できない事実――を分離するのは一仕事だ。ゆるぎない事実を起点として導ける推論、そして全体像が明らかになる特異点、これを見つけるのが、与えられた仕事だ。火曜の夜、馬のオーナーのロス大佐と事件を担当するグレゴリー警部の両方から、協力要請の電報が来た」
「火曜の夜!」私は叫んだ。「もう木曜の朝だぞ。なぜ昨日行かなかったんだ?」
「大失敗だ、ワトソン。残念だが、僕はこういうヘマをよくやる。君の事件簿の読者が想像するより、ミスは多いんだ。実は、ここまで注目されている馬を長く隠しておけるはずがないと思っていた。とくにダートムーア北部のような田舎では、考えられなかった。昨日はずっと、馬が見つかり、それを連れ去った人物がジョン・ストレイカー殺人容疑で逮捕されるニュースを待っていた。しかし今朝、フィッツロイ・シンプソンの逮捕以降、進展がなかったと知り、重い腰を上げるときが来たと感じた。とはいえ、昨日を無駄に過ごしたわけではないと思う」
「じゃあ、何か結論が出たのか?」
「少なくとも、事件の重要な事実はしっかり把握した。それを君にひとつずつ、説明していこう。見落としの確認には、人に説明するのが一番だし、協力してもらうなら、調査の開始点をはっきりさせておくべきだ」
私は煙草を吸いながら、シートに寄りかかった。ホームズは身を乗り出し、細い人差し指で左の掌にチェックマークを入れながら、遠征の原因となった事件の概要を説明し始めた。
「シルバー・ブレイズは」ホームズは言った。「名馬アイソノミー系で、祖先馬に負けない素晴らしい成績を残している。今5歳馬だが、幸運なオーナー、ロス大佐は何度も賞金を獲得している。今回の不幸な事件までウェセックス・カップの本命馬で、オッズは3-1だった。これほど低い賭け率でも、シルバー・ブレイズは競馬ファンの間で、不動の1番人気で、しかもこれまで、期待はただの1度も裏切られなかった。だからこんなにオッズが低くても、シルバー・ブレイズへの賭け金は莫大な額になっている。つまり来週火曜日の競馬が始まる瞬間、できればシルバー・ブレイズが競馬場に現れるのを阻止したい人間が大勢いるのは明らかだ」
「もちろん、大佐の調教厩舎が設置されているキングズ・パイランドでも、こういった危険性はきちんと認識しており、シルバー・ブレイズの警護にあらゆる予防策がとられていた。ジョン・ストレイカーは、元はロス大佐の馬の騎手だったが、体重超過で調教師になった男だ。彼は騎手として5年間、その後調教師として7年間、大佐に仕えた。ジョン・ストレイカーはずっと熱心で真面目な使用人で、彼の部下に3人の馬丁がいた。小さな施設なので、馬は全部で4頭だけだ。3人の馬丁のうちひとりが、毎晩厩舎で寝ずの番をし、他のふたりは屋根裏で寝る。3人とも、真面目な性格だ。ジョン・ストレイカーは既婚者で、厩舎から200メートルほど離れた小さな住宅に住んでいる。子供はなく、メイドがひとりいて何不自由なく暮らしている。このあたりは田舎で、住人は非常に少ない。しかし北に800メートルほど行くと、そこにはタヴィストックの建築業者が建てた小さな住宅の集落がある。これは、ダートムーアのきれいな空気を吸いに来る静養者などが利用する施設だ。タヴィストックは荒野の3キロ西にあり、同じく3キロ離れた場所に、キングズ・パイランドより大きなメイプルトンの訓練設備がある。これはバックウォーター卿が所有しており、管理人はサイラス・ブラウンだ。荒野の他の方向には、どこにも住居はなく、未定住のジプシーが少しいるだけだ。これが事件が発生した月曜の夜の状況だ」
「その夜、馬は普段通りに運動して水を飲み、夜9時、厩舎の鍵が掛けられた。馬丁のふたりが調教師の家に行って台所で夕食をとる間、3人目のネッド・ハンターが残って見張りをしていた。9時ちょっと過ぎにメイドのエディス・バクスターが厩舎に夕食を届けに行った。献立はマトンのカレー煮だが、飲み物は持参しなかった。厩舎には蛇口があり、勤務中の馬丁はそこの水しか飲まない決まりだったからだ。道が非常に暗く、荒野を横切っていたため、彼女はランタンを下げていた」
「エディス・バクスターが厩舎の手前25メートルくらいまで来たとき、ひとりの男が闇の中から現れ、彼女を呼び止めた。その男がランタンに照らされた光の輪の中に踏み入ると、灰色のツイードを着て布製の帽子をかぶった、紳士風の姿が見えた。男はゲートルを巻き、握りがついた太いステッキを持っていた。しかし彼女の印象に最も強く残ったのは、非常に青ざめた顔と落ち着きのない態度だった。年齢は少なくとも30歳過ぎに見えた」
「『ここはどこですか?』男はたずねた。『荒野で野宿するしかないと、あきらめかけたところで、そのランタンの光が見えました』」
「『キングズ・パイランドの訓練厩舎近くです』メイドは言った」
「『そうですか、なんと幸運な!』男は叫んだ。『厩舎の馬丁が毎日ひとりで泊まっているらしいですが、持っているのは、きっとその馬丁の夕食ですね。ねえ、ドレスが新調できるお金を断るほど、あんたは気取り屋じゃないでしょう?』男はベストのポケットから折り畳んだ白い紙を何枚か取り出した。『今夜厩舎にいる馬丁にこれを渡してくれれば、素晴らしいドレスを買えるくらいのお礼はするから』」
「メイドは、男の熱心な態度に怖くなり、脇をすり抜け、いつも食事を届けていた窓へ走った。窓は開いていて、ハンターは厩舎内の小さなテーブルの前に座っていた。彼女が起きたことを説明し始めたとき、男が再び近寄って来た」
「『こんばんは』男は窓からのぞき込みながら言った。『ちょっと、きかせて欲しいんだが』メイドは、男が話しているとき、握った手から小さな紙の端が出ていたのに気づいたと証言している」
「『ここに何の用だ?』ハンターはきいた」
「『君のふところが暖かくなるかもしれないという用さ』その男は言った。『ウェセックス・カップ出場馬のシルバー・ブレイズとバヤードがここにいるだろう。確かな情報を教えてくれれば、絶対に損はさせない。現在の負担重量なら、バヤードは本命馬に5ハロンで100メートル離せるから、厩舎の人はこの馬に賭けているという噂があるが、本当なのか?』」
「『お前は、ケチな予想屋か!』ハンターは叫んだ。『キングズ・パイランドではどういう扱いをするか見せてやる』ハンターはさっと立ち上がると、犬をけしかけるために、厩舎の中を走って行った。エディス・バクスターは家に逃げ帰ったが、途中で振り返ると、男が窓に身を乗り入れているのが見えた。しかし1分後、ハンターが犬を連れて飛び出して来たとき、男の姿はなかった。ハンターは建物の周辺を駆け足でくまなく探し回ったが、男の手掛かりはなかった」
「ちょっと待ってくれ」私はたずねた。「馬丁が犬を連れて出たとき、扉に鍵を掛けたのか?」
「やるな、ワトソン、よく気づいた!」ホームズはつぶやいた。「それは重要な点で、僕も非常に気になったので、昨日ダートムーアにわざわざ電報を打って確認したが、馬丁は出る前に鍵を掛けていた。ついでに言えば、窓は人が通れる大きさではなかった」
「ハンターは同僚の馬丁が戻って来るのを待って、調教師のストレイカーに事件を伝えた。ストレイカーは、それを聞いて怒り狂ったが、この時点ではまだ、事件の本当の重要性を知らなかったのかもしれない。だが彼はこの出来事で、なんとなく胸騒ぎがしたらしく、ストレイカー夫人が午前1時に目を覚ますと、夫が服を着ているのに気づいた。どうしたのかとたずねると、馬が心配で眠れないので厩舎に行って無事を確認するつもりだ、と答えた。雨が窓を打つ音が聞こえたので、夫人は家にいるように頼んだ。それでも、ストレイカーは大きな雨合羽を着て出て行った」
「夫人は朝7時に目覚めたが、夫がまだ戻っていないのに気づき、急いで服を着ると、メイドを呼んで厩舎に出かけた。扉は開いたままで、中にいたハンターは椅子で丸まったまま、完全な昏睡状態だった。シルバー・ブレイズの馬房は空で、夫の姿はどこにもなかった」
「馬具置き場の上にあるワラ切り部屋で寝ていたふたりの馬丁が、すぐに起こされた。どちらも眠りの深い男だったので、夜中に物音は聞いていなかった。ハンターは、強力な薬物が効いているらしく、意識を取り戻さないため、夫人とメイドはふたりの馬丁と一緒に、行方不明の夫と馬を探しに、外に駈け出した。4人はまだ、ストレイカーが何らかの理由で、馬を早朝の運動に連れ出したかもしれない、と期待していた。しかし近くの荒野全体を見渡せる小山に登ると、失踪した馬の姿はなく、代わりに惨劇の証拠が目に入った」
「厩舎から400メートルほど離れたハリエニシダの小枝にジョン・ストレイカーのコートがはためいていた。そのすぐ向こうの荒野に、すり鉢状になった窪地があり、その底からジョン・ストレイカーの死体が発見された。頭部を鈍器のようなもので激しく殴られ、頭蓋骨が砕けており、腿には鋭利な刃物で切り裂かれたような、大きな傷があった。しかし、ストレイカーは襲撃者に必死で抵抗したらしく、右手には握りの部分までべっとりと血に染まった小さなナイフが握られ、左手には、赤と黒の絹のネクタイが握り締められていた。そのネクタイは前の夜、厩舎にやって来た不審者が締めていたものだと、メイドのエディス・バクスターが証言している。昏睡から覚めたハンターも、そのネクタイを締めていた男をはっきり覚えていた。ハンターは、その男が厩舎を無防備にするため、窓からマトンのカレー煮に薬物を入れたに違いないと考えている。失踪した馬だが、格闘時、その場にいたことを示す足跡が、窪地になっている現場のぬかるみ一面についていた。ところが馬はそれ以降、姿を消し、巨額の報奨金を目当てに、ダートムーア中のジプシーが血まなこで探しているのに、まだ発見の報告はない。最後に、ハンターの夕食の残りを分析すると、多量の阿片粉末が検出された。ところが、その夜に同じものを食べた人間には異常がなかった」
「以上が、憶測をすべて排除し、可能な限り整理した、事件の主要な事実関係だ。次に警察の調査について、簡単に説明しよう」
「事件を担当しているグレゴリー警部は、非常に有能だ。想像力に恵まれていれば、かなりの地位まで昇進するかもしれない。現場に到着すると、グレゴリー警部はただちに、最重要容疑者を発見して逮捕した。その容疑者は僕がさっき言った住宅の一軒に宿泊していたから、見つけること自体は、さほど難しくない。新聞によると、男の名前はフィッツロイ・シンプソンだ。上流階級の生まれで、いい教育を受けているが、競馬で財産を使い果たし、今はロンドンのスポーツクラブで細々と上品な私設馬券を販売して生計を立てている。シンプソンの賭け帳を調べると、対抗馬に5000ポンド賭けていることがわかった。逮捕時、シンプソンは自主的に、ここに来た理由はキングズ・パイランドの馬や、メイプルトン厩舎のサイラス・ブラウンが管理している2番人気のデズバラについて、情報を得たかったためだと供述した。メイドが証言した前夜の行動は認めたものの、直接情報を得るためで、悪いことをするつもりではなかったと主張している。自分のネクタイを見せられて、シンプソンは真っ青になり、殺された男が握っていた理由をきかれても、説明できなかった。シンプソンの服は濡れており、前夜、嵐の中を外出していたことは確かだ。そして、彼の鉛入りペナン・ステッキは、複数回殴打すれば、ストレイカーを殺傷した凶器にもなりうる。一方、ストレイカーのナイフの血痕を考えれば、犯人はどこかを負傷しているはずだが、シンプソンの体に傷はない。簡単に説明すれば、以上だ、ワトソン。これで何か気づくことがあれば、非常に助かる」
私はホームズ独特の簡潔さで語られたこの話に、激しく興味をひかれて聞き入っていた。ほとんどが知っていた事実とはいえ、重要な点とそうでない点をきちんと比較検討できていなかったし、相互の関連性もよく理解していなかった。
「こういう可能性はないかな」私は言った。「ストレイカーは、脳に損傷を受けた後、けいれんを起こしてもがき、自分のナイフで自分を切ったというのは」
「ないどころか、十分可能性がある」ホームズは言った。「そうなると、シンプソンに大きく有利な要素がひとつ消える」
「しかし」私は言った。「これで警察がどんな主張をするつもりなのか、わからないな」
「何であれ、こっちの判断とは真逆だろうな」ホームズは答えた。「あくまでも想像だが、警察のシナリオはこんなものだろう。フィッツロイ・シンプソンは、馬丁に薬を盛る。彼はあらかじめ合鍵を用意しており、おそらく馬をどこかに隠すつもりで厩舎の扉を開け、馬を連れ出す。手綱がなくなっていたが、それはシンプソンが馬につけたからだ。その後、扉を開けたまま、荒野に馬を連れて行く。そのとき、シンプソンはストレイカーと出くわすか、追いつかれる。当然格闘となり、シンプソンはストレイカーの自衛用の小刀では、かすり傷ひとつ負わず、重いステッキでストレイカーの頭を打ち砕く。その後、馬をどこかの隠し場所に連れて行く。さもなければ、馬は格闘中に逃走し、今も荒野のどこかをうろついている。事件に対する警察の見方は、ざっとこんなところだろう。ちょっと無理筋だが、他の線は、もっと筋が悪いからな。しかし現場についたら、すぐに自分で調査を開始するつもりだ。それで、どこまで進展が見込めるか、今はまだ何とも言えない」
ダートムーアの大きな輪の中央に、まるで楯のつまみのように突き出ているタヴィストックの小さな街に着くころには、日は傾いていた。駅ではふたりの男性が待っていた。ひとりは背が高く、髪とあごひげがライオンのような金髪の男で、好奇心に豊んで洞察力のありそうな空色の瞳をしていた。もうひとりは背が低く、機敏そうな、上着とゲートルに身を包んだこざっぱりとした男で、ほおひげを短くきちんと刈り、メガネをかけていた。この人物が有名なスポーツ愛好家のロス大佐で、もうひとりが警察でめきめきと頭角を現し始めているグレゴリー警部だった。
「わざわざご足労いただき感謝します、ホームズさん」ロス大佐は言った。「こちらの警部さんには、全力を尽くしていただいていますが、自分の馬を取り戻し、ストレイカーの仇を討つため、何でもやっておきたいのです」
「捜査の進展は?」ホームズがたずねた。
「残念ですがほとんどありません」グレゴリー警部が言った。「馬車を待たせてあります。日没前に現場を確認したいでしょうから、馬車の中でお話ししましょうか」
1分後、乗り心地の良いランドー馬車にゆられながら、古風なデヴォンシャーの町を進んでいた。グレゴリー警部は事件に夢中らしく、口数が多かった。ホームズはときどき質問をしたり、あいづちを打ったりした。ロス大佐は腕を組み、帽子を目深にかぶってシートにもたれていたが、私はふたりの話を興味深く聞いていた。グレゴリー警部は自分なりの見解をまとめていたが、それはホームズが列車の中で言っていたこととほとんど変わらなかった。
「フィッツロイ・シンプソンの容疑は固まりかけています」グレゴリー警部は言った。「犯人はシンプソンだと確信していますが、状況証拠しかないので、何か新事実があれば簡単に崩されることもわかっています」
「ストレイカーのナイフはどうなった?」
「倒れた際、自分で傷をつけたという結論になりました」
「友人のワトソン博士が、可能性があると列車で言っていた説だな。それが正しければ、シンプソンという男性には不利だ」
「その通りです。彼はナイフも持たず、怪我もないが、確実な犯行の証拠がある。最初に、本命馬の消失に非常に強い利害関係があった。次に、馬丁に薬を盛った疑惑がある。さらに、嵐の中を重いステッキという武器を持って外出していた。その上、彼のネクタイが死んだ男の手から見つかった。これで、陪審に提出する証拠としては十分だと思います」
ホームズは首を振った。「有能な弁護士なら、全部論破できるな」ホームズは言った。「なぜ馬を厩舎から連れ出さねばならんのだ?傷つける気なら、なぜその場所でしないのか?合鍵はどこだ?粉末阿片を売った薬剤師は誰だ?土地勘のないシンプソンが、こんな有名な馬をどこに隠せるのか?彼は、馬丁に渡して欲しいとメイドに見せた紙は、何だと説明しているんだ?」
「10ポンド紙幣だと言っています。財布に入っていました。しかし、他の疑問は、思うほど手ごわくはありません。シンプソンは、2度ほど夏にタヴィストックまで宿泊に来ており、この地に不慣れではありません。阿片はロンドンで買ったのでしょう。鍵は、使った後に捨てたんです。馬はムーアの古い炭鉱か、穴の底かもしれません」
「ネクタイについての供述は?」
「自分のものだと認めていますが、紛失したと言っています。しかし事件について新事実が判明しましたので、シンプソンが馬を厩舎から連れ出した理由が説明できるかもしれません」
ホームズは耳をそばだてた。
「月曜の夜、殺人現場から2キロもない場所でジプシーが野営していた跡を見つけました。火曜日には姿を消していましたが、このジプシーがシンプソンの共犯だとします。シンプソンが追いつかれたとき、馬をジプシーに届けるところだったとすれば、今、馬を連れているのはそのジプシーではないでしょうか?」
「確かにその可能性はある」
「問題のジプシーを発見するため、荒野をしらみつぶしに調査しています。半径16キロ以内にあるタヴィストックの厩舎や納屋も全部調べました」
「すぐ近くに別の訓練厩舎があるらしいが?」
「ええ、まず調査すべき場所ですからね。そこの馬、デズバラは2番人気で、本命馬がいなくなれば有利です。調教師のサイラス・ブラウンは、この競馬にかなり賭けているようですし、ストレイカーとは仲が悪かった。しかし、厩舎を調べましたが、今回の事件に関係ありそうなものは何も見つかりませんでした」
「さらに、その厩舎を調査したがっていたシンプソンが来た痕跡も見つからなかったわけだ」
「まったくありませんでした」
ホームズは馬車のシートにもたれかかり、会話はとぎれた。数分後、道沿いに建っている、ひさしが突き出た小奇麗な赤レンガの邸宅の前で、御者が馬車を停めた。パドックの少し先に、長い灰色のタイルの離れがあった。それ以外はどこを見回しても、しおれたシダで茶色になった低くうねる荒地がはるか先まで広がり、それをさえぎるものは、タヴィストックの尖塔と、メイプルトン厩舎がある西方向の集落だけだった。ホームズ以外は全員下車したが、ホームズはシートにもたれ、前方の空をにらんだまま、完全に自分の考えに没頭していた。私がホームズの腕に触れたとき、やっとビクッとして気がつき、馬車から降りた。
「申し訳ありません」ホームズは、驚きの目で見つめていたロス大佐の方を向いて言った。「白昼夢を見ていました」ホームズの目には輝きがあり、その仕草には興奮をおさえている気配があった。これを見て、ホームズの態度をよく知っている私は、彼が何か手掛かりをつかんだと確信した。しかし、どこで発見したのかは想像もできなかった。
「多分、まず事件現場に行きたいですよね?ホームズさん」グレゴリー警部が言った。
「その前に、細かい質問をいくつかしたいですね。ストレイカーの遺体はここに運ばれていますね?」
「ええ、上の階に安置しています。検死は明日です」
「ロス大佐、ストレイカーはあなたの元で働いて、もう何年にもなりますよね?」
「ずっと真面目に働いてくれました」
「警部、ストレイカーが殺されたときの所持品一覧を作っていますか?」
「ホームズさんがご覧になりたいかもしれないと思って、居間に置いてあります」
「それはありがたい」我々は順に居間に入ると、中央のテーブルを囲んで座った。警部は四角いブリキ箱の鍵を開け、中のものを積み上げた。蝋マッチの箱、5センチの樹脂ロウソク、A D P と文字の入ったブライヤーの根のパイプ、キャベンディッシュ長切り30g入りのアザラシ革の袋、金鎖つき銀製時計、ソブリン金貨5枚、アルミ製筆箱、紙が数枚、ロンドン・ウェイス&Co. と銘の入った、柄が象牙製で刃先が非常に薄く折れやすそうなナイフがあった。
「妙な刃物だな」ホームズは、ナイフを手にとって入念に調べながら言った。「血痕があるから、おそらくストレイカーが握っていたものだろう。ワトソン、この刃物はきっと君の仕事関係だな?」
「医療分野では白内障メスと呼んでいる」私は言った。
「そうだと思った。この繊細な刃は非常に細かな作業用だ。男が外出時に持ち歩くにしては妙だな。とくに、ポケットには入れにくい」
「切っ先に丸いコルクがあり、死体の側で見つかりました」グレゴリー警部が言った。「夫人の証言では、そのナイフは鏡台に置いてあり、部屋を出る際、持ち出したということです。武器としてはお粗末ですが、おそらくそのとき、手近にある中では、一番ましだったのでは」
「まあ、そうかもしれない。この紙は?」
「3枚は飼い葉業者の領収書です。1枚はロス大佐の指示書です。最後の1枚は、ボンド街の服飾店マダム・ルジュリエからウィリアム・ダービシャー宛の37ポンド15シリングの請求書です。夫人の供述では、ダービシャーとは夫の友人で、ときどき手紙が来ていたらしいです」
「ダービシャーの妻はちょっと高級品志向だな」ホームズは請求書をちらりと見ながら言った。「1着で22ギニーとは結構な値段だ。しかし、もう調べるものはなさそうだから、殺人現場に向かいましょうか」
我々が居間から出て来ると、廊下で待っていた女性が歩み寄って、警部の袖に手を置いた。やつれて弱々しく、必死の形相で、つい最近の恐怖が顔に焼きついていた。
「わかりました?何かわかりましたか?」彼女は息を詰まらせた。
「まだです、ストレイカーさん。しかしこちらのホームズさんがロンドンから応援に来てくださいました。警察でも、全力を尽くします」
「最近、プリマスのガーデンパーティでお会いしましたね、ストレイカーさん?」ホームズは言った。
「いいえ、人違いです」
「え、そうですか?間違いないはずです。奥さんはダチョウの羽の縁飾りがついた赤っぽいグレーのドレスを着ていました」
「そんな服は持っていません」ストレイカー夫人は答えた。
「ああ、では人違いですね」ホームズは失礼を詫びてから、グレゴリー警部に続いて外に出た。荒野を少し歩くと、死体が見つかった窪地に着いた。その縁にハリエニシダの茂みがあり、コートはその上にあった。
「その夜は風がなかったと、聞いているが」ホームズは言った。
「ありませんでした。しかし非常に激しい雨が降っていました」
「そうであれば、コートは飛ばされてハリエニシダに引っかかったのではなく、そこに置いたことになるな」
「そうです。ハリエニシダの上に置かれていました」
「それは非常におもしろい。地面はかなり踏み荒らされているようだ。もちろん、月曜の夜以降、大勢が歩いただろうな」
「こちらの端に敷物を敷いて、全員そこに立ちました」
「素晴らしい」
「このバッグの中に、ストレイカーの靴が1足、フィッツロイ・シンプトンの靴が1足、シルバー・ブレイズの蹄鉄が入っています」
「警部、見事だ!」ホームズはバッグを受け取って窪地に下りて行き、敷物をもっと中央に移動した。それからうつ伏せになって、手の上にアゴを乗せ、目の前の踏み荒らされたぬかるみを慎重に調べた。「おや!」突然ホームズが言った。「これは何だ?」それは半分燃えた蝋マッチで、あまりにも泥まみれだったので、一見、木クズに見えた。
「そんなものを見落とすとは」グレゴリー警部は、とまどいながら言った。
「土に埋まって見えなかったからね。探していたから見つかっただけだ」
「まさか!見つかると知っていたのですか?」
「見つかりそうだと思っていた」
ホームズはバッグから靴を取り出し、ひとつずつ、地面についた足跡と見比べた。それから窪地の縁まで上がり、シダと茂みの間を這い回った。
「申し訳ないですが、そこにはもう手掛かりはないと思います」グレゴリー警部は言った。「半径100メートルの範囲は、くまなく調べました」
「なるほど!」ホームズは起きあがって言った。「君がそう言うなら、調べ直すのは失礼だな。しかし今日中に現場をよく知りたいので、日が暮れる前に荒野を少し歩いて行こうと思う。この蹄鉄は幸運のお守りに持って行くよ」
ホームズの無言で体系だった仕事ぶりに、イライラするそぶりを見せていたロス大佐は、時計をちらっと見た。「警部さん、一緒に戻りませんか」ロス大佐は言った。「いくつか助言を頂きたいことがあります。とくに、シルバー・ブレイズの出走中止を発表すべきかどうか」
「その必要はありませんよ」ホームズは自信満々に叫んだ。「僕が必ず出走させてみせます」
ロス大佐は会釈し「そのお言葉に感謝します」と言った。「警部と私はストレイカーの家にいます。散歩がすんだら、馬車でタヴィストックまで一緒に戻りましょう」
ロス大佐はグレゴリー警部と一緒に戻った。ホームズと私はゆっくりと歩きながら荒野を横切って行った。太陽はメイプルトン厩舎の向こうに沈み始めていた。そして目の前の長く傾斜した大地は金色に染まり、しおれたシダとイバラが夕陽を浴びている場所は濃い赤茶になっていた。しかし、自分の考えに非常に深くのめり込んでいるホームズにとって、この壮観な景色は何の意味もなかった。
「こっちだ、ワトソン」ホームズはついに言った。「今は、ジョン・ストレイカー殺人は後回しにして、馬の行方を突き止めることに専念しよう。馬が殺人事件の最中か事件後に逃げ出したなら、どこに行くか?馬は群居性が強い動物だ。放っておけば、本能的にキングズ・パイランドに戻るかメイプルトン厩舎に行くだろう。荒野を駆け回ってどうする?絶対に今までに発見されているはずだ。ではジプシーが馬を連れ去る動機があるか?ジプシーはもめごとが起きたと聞けばすぐに去る。警察に尋問されたくないからだ。ジプシーに馬を売るツテはないから、大変な危険を冒して連れて行っても、得るものはない。これは明白だ」
「では、どこにいるんだ?」
「言った通り、馬はキングズ・パイランドかメイプルトンに行ったはずだ。だがキングズ・パイランドにはいない。したがって、今メイプルトンにいる。これを作業仮説としよう。そしてこの仮説から何が導き出されるか考えよう。グレゴリー警部が言ったように、荒野のこの周辺は乾燥してカチカチだが、メイプルトンの方角に下っている。向こうに細長い窪地が見えるだろう。きっと月曜の夜には非常にぬかるんでいたはずだ。予想通りなら、馬はあそこを横切っている。馬の足跡を探すならあの場所だ」
ホームズがこう話している間も、私たちはキビキビと歩き、その窪地まで、あと数分の場所まで来た。ホームズは私に土手の右側に行くように指示し、彼は左に回った。しかし50歩も歩かないうちに、ホームズが歓声を上げ、手まねきするのが見えた。目の前の柔らかい地面に、くっきりと馬のひづめの跡があった。その跡にポケットに入れて来た蹄鉄を当てると、ぴたりと一致した。
「想像力の成果を見たか」ホームズは言った。「これがグレゴリー警部に、欠けているもののひとつだ。最初に起きえたことを想像し、その仮説を元に行動し、今それが正しいと証明された。さあ先を急ごう」
湿地の底を横切り400メートルほどの乾いた固い芝地を過ぎた。地面はまた斜面になり、再び足跡が見つかり、それから800メートルほど見失ったが、メイプルトンにごく近い場所でまた見つかった。先にその足跡を見つけたホームズは、勝ち誇った表情で立ったまま指差していた。馬の脇に人間の足跡があった。
「ここまでは馬だけだったのに」私は叫んだ。
「そうだ。ここまでは馬だけだった。おや、これは何だ?」
ふたつの足跡は急に曲がって、キングズ・パイランドの方向へ向かっていた。ホームズは口笛を吹き、ふたりでその跡をつけた。ホームズは足跡から目を離さなかったが、私が偶然ちょっと脇見をしたとき、驚いたことに同じ足跡が逆方向に戻って来ていた。
「お手柄だな、ワトソン」私の指摘に対してホームズが言った。「おかげで長い距離を歩く時間が節約できた。自分の足跡をまた戻って来るはめになっていただろう。戻って来ている足跡を追おう」
それほど遠くまで行く必要はなかった。足跡はメイプルトン厩舎の門に続くアスファルト舗装の道で終わっていた。近づくと、中から馬丁が飛び出して来た。
「この辺をウロウロするな」馬丁は言った。
「ひとつだけききたいことがある」ホームズはベストのポケットに指を入れて言った。「もし明日の朝5時に来たら、君の主人のサイラス・ブラウンはまだ起きていないかな?」
「まさか。親方はいつでも一番に活動を始める人だから、親方より早起きの人はいませんよ。しかし本人がやって来ましたよ。ちょっと困ります。あなたからお金をもらうのを見られたら、首が危ない。よければ後で」
シャーロックホームズがポケットから出していた半クラウン金貨をまた戻したとき、いかつい目つきをした年配の男が、狩猟用鞭を手に大股で門から出て来た。
「何をしている、ダンソン!」主人は叫んだ。「無駄話をするな!仕事に戻れ。それからお前ら、ここに何の用だ?」
「10分ほど、お話ししたいのですがね」ホームズは非常に穏やかに言った。
「暇な奴らと話している時間などあるか。部外者の来るところじゃない。出て行け!犬をけしかけるぞ」
ホームズは体を前に傾けて男の耳に何かささやいた。彼は激しく動揺し、コメカミまで真っ赤になった。
「それは嘘だ!」主人は叫んだ。「ひどいデタラメだ!」
「いいでしょう。こんな往来で議論する気ですか?それとも居間で話しますか?」
「ああ、よければ入ってくれ」
ホームズはほほえんで「数分以上は待たせないよ、ワトソン」と言った。「さあ、ブラウンさん、すべてあなた次第ですよ」
20分が過ぎて、ホームズとブラウンが再び現れたとき、真っ赤だったブラウンの顔は青ざめていた。こんな短い間にサイラス・ブラウンに訪れたような変化は、これまで見たことがなかった。ブラウンの顔は灰のように白く、額には玉のような汗をかき、手はブルブル震えて、狩猟用の鞭が風にそよぐ小枝のように揺れていた。すごんだ高圧的な態度はすっかり影をひそめ、主人に従う犬のように、ホームズの隣に縮こまってついて来ていた。
「あなたのご指示通りにします。すべてそのようにします」ブラウンは言った。
「くれぐれも間違いがないようにな」ホームズはブラウンを振り返りながら言った。ブラウンはホームズの目に恐れをなしてたじろいだ。
「ああ、いえ、絶対に間違いはありません。必ず持って行きます。最初に変更しておきましょうか?」
ホームズはちょっと考えて、突然笑い出した。「いや、しなくていい」ホームズは言った。「後で手紙を出す。もう、ごまかしはなしだ。さもないと……」
「ああ、信用してください。私を信用してください!」
「もちろん、信用するとも。まあ、明日連絡する」ホームズは差し出された震える手を無視して振り返り、キングズ・パイランドへ向かった。
「サイラス・ブラウンほど、威張っているわりに意気地なしでずるい奴にはめったにお目にかかれないな」 ホームズは並んで歩いているときに言った。
「それじゃ彼が馬を持っているのか?」
「威張り散らしてごまかそうとしたが、僕があの朝のあいつの行動を、寸分たがわず正確に説明したら、見られていたと思い込んだらしい。もちろん君も、爪先が妙に角ばった足跡と、それにぴったり対応するあいつの靴を見ただろう。言うまでもないが、下っ端の人間が危険をおかしてやることじゃない。僕はあいつに、いつものように朝一番先に起きて、妙な馬が荒野をうろついているのを見つけたときの状況を説明してやった。さらに、その馬に近より、本命馬の名前の元となった白い額を見て、自分が金を賭けている馬を負かすことができるただ1頭の馬が、偶然にも自分の手中にあるのに気づいて、どんなに驚いたのかもな。それから、最初はすぐに馬をキングズ・パイランドに返そうと思ったものの、競走が終わるまで隠しておきたい誘惑に勝てず、メイプルトンに連れて帰って隠したことを説明してやった。何もかも話してやったら、降参して、自分の身を守ることしか頭になくなったようだ」
「しかしブラウンの厩舎は捜索を受けたんだろう?」
「それは、あいつのように馬に詳しい男なら、ごまかす方法はいくらでもある」
「しかし馬を預けて心配はないのか?傷つける動機は十分にあるぞ?」
「ワトソン、あいつはあの馬を我が子のように守るよ。馬を安全に管理する以外に、見逃してもらえるチャンスはないとわかっているからな」
「私の印象では、ロス大佐は馬が無事に帰っても、それだけで見過ごすような人間には思えなかったが」
「ロス大佐は関係ない。僕は自分のやり方で行動し、話すべきと思ったことだけを話す。これは僕が警官でない強みだ。ワトソン、気づいたかもしれないが、大佐は僕に少し横柄な態度だった。ちょっとお返しをする気になっている。大佐には馬のことは黙っていてくれ」
「君の許可なしには言わないよ」
「もちろん、これは誰がジョン・ストレイカーを殺したかということに比べればまったく小さな問題だ」
「君はそっちに注力するつもりか?」
「まさか。一緒に夜行列車でロンドンに帰ろう」
この言葉には非常に驚かされた。デヴォンシャーに来て、まだ数時間しかたっていない。そして着手早々、これほど見事な成果を上げた捜査をあっさり放棄するとは、私には意味不明だったが、ストレイカーの家に戻るまで、ホームズからそれ以上の話をきき出すことはできなかった。ロス大佐とグレゴリー警部は居間で待っていた。
「友人と私は夜行特急でロンドンに戻ります」ホームズは言った。「きれいなダートムーアの空気のおかげで、さっぱりしました」
グレゴリー警部は目を見開き、ロス大佐はあざ笑うように口をゆがめた。
「それではストレイカーを殺した犯人の逮捕をあきらめるとおっしゃるのですか」ロス大佐は言った。
ホームズは肩をすくめた。「確かにそれは非常に困難でしょうね」ホームズは言った。「しかし、大佐の馬が火曜日に出走できることは、まず間違いありませんので、騎手の準備をお願いします。ジョン・ストレイカーの写真を1枚いただけますか?」
警部は封筒から1枚取り出してホームズに渡した。
「グレゴリー警部、僕が必要なものを全部お見通しだ。エディス・バクスターにききたいことがあるので、ここでちょっとお待ちいただけますか」
「ホームズさんにはかなり、失望しました」ホームズが部屋から出て行ったとき、ロス大佐が吐き捨てるように言った。「あの人が来てから何の進展もなかった」
「少なくとも馬が出走できると保証されたでしょう」私は言った。
「ええ、口約束ですがね」ロス大佐は肩をすぼめながら言った。「本当は馬を取り返して欲しかったところですよ」
私が弁護をしようとしたとき、ホームズが部屋に戻って来た。
「さて、皆さん」ホームズは言った。「そろそろタヴィストックに向かいましょうか」
馬車に乗り込む間、馬丁が扉を開けていてくれた。ホームズは突然何かを思いついたようで、体を乗り出して馬丁の肘に触れた。
「パドックで少し羊を飼っているね」ホームズは言った。「面倒は誰が見ているんだ?」
「僕です」
「最近何か問題は起きていないか?」
「とくに大きな問題はないです。そう言えば、足を引きずるようになったのが3頭いますが」
ホームズはククッと笑って手をこすり合わせ、非常に満足そうな様子だった。
「大穴だ、ワトソン、大変な大穴を当てたぞ」ホームズは私の腕をギュッと握って言った。「グレゴリー、羊の奇妙な伝染病に注目するように勧めるよ。馬車を出してくれ」
ロス大佐はまだホームズを見下したような表情をしていたが、グレゴリー警部はハッとした様子だった。
「重要だとお考えなんですね?」グレゴリー警部はたずねた。
「この上なく重要だな」
「他に、気をつけなければならない点がありますか?」
「あの晩の犬の奇妙な行動だ」
「犬はあの夜、何もしませんでしたが」
「それが奇妙な行動なのだ」ホームズは言った。
4日後、ホームズと私はウェセックス・カップを見るために、再び列車でウィンチェスターに向かった。ロス大佐は約束通り駅の外まで迎えに来ており、彼の馬車で街の向こう側にある競馬場に向かった。ロス大佐はむっつりした顔で、この上なく、よそよそしい態度だった。
「私の馬はまだ現れていませんがね」ロス大佐は言った。
「見ればわかるんですね?」ホームズは言った。
ロス大佐はむっとした。「20年間競馬界にいて、そんな質問をされたことはこれまで一度もない」ロス大佐は言った。「顔の大流星と右前足の白を見れば、子供でもシルバー・ブレイズだとわかる」
「オッズはどうなっていますか?」
「それが、妙なんです。昨日は15-1で買えたのに、どんどん差がなくなり、今は3-1でもなかなか買えません」
「フン!」ホームズは言った。「情報をつかんだ奴がいるな。そうに違いない」
馬車が正面特別観覧席の囲いの前に来たとき、私は参加馬の掲示をながめた。
ウェセックス杯。出走登録料50ソブリン。出走取消半額没収、スポンサー追加金1000ソブリン、4〜5歳馬。2着300ポンド。3着200ポンド。新コース(2600m)。
1. ヒース・ニュートン氏のザ・ニグロ。(赤帽。シナモンの上着)。
2. ウォードロー大佐のピュージリスト。(ピンク帽 青と赤の上着)。
3. バックウォーター卿のデズバラ。(黄帽と黄袖)。
4. ロス大佐のシルバー・ブレイズ。(黒帽。赤の上着)。
5. バルモラル公爵のアイリス。(黄色と黒の縞模様)。
6. シングルフォード卿のラスパー。(紫の帽子。黒袖)。
「もう1頭は出走を取り消して、ホームズさんの言葉にすべての希望を賭けました」ロス大佐は言った。「おや、これは何だ。シルバー・ブレイズが本命だと?」
「5-4でシルバー・ブレイズ!」賭屋がどなった。「5-4でシルバー・ブレイズ!15-5でデズバラ!5-4で本命以外!」
「出走馬が来る」私は叫んだ。「全部で6頭だ」
「全部で6頭?では私の馬もいるのか」ロス大佐は感きわまって叫んだ。「しかし見えんぞ。私の色は通っていない」
「まだ5頭しか通っていないので、次でしょう」
私がそう言うと、計量の囲いから力強い栗毛の馬がさっと姿を現し、大佐の有名な黒と赤の騎手を乗せて、駈歩で目の前を横切った。
「あれは私の馬ではない」ロス大佐は叫んだ。「あの馬には白い毛がない。何をしたんですか、ホームズさん?」
「まあ、まあ、走りっぷりを見ましょう」ホームズは涼しげに言うと、数分間私の双眼鏡で観察していた。「いいぞ!素晴らしいスタートだ!」ホームズは突然叫んだ。「ほら、あそこです。コーナーを曲がって来る!」
車内から、馬が直線に差しかかる素晴らしい光景が見えた。6頭の馬は、カーペット1枚分ほどの集団になっていたが、そこで、デズバラが抜け出した。しかし、正面に来るまでに逃げ足が急に衰え、大佐の馬があっさり差すと、6馬身以上の差をつけてゴールした。かなり遅れた3着は、バルモラル公爵のアイリスだった。
「ともかく勝ったようだな」ロス大佐は額の汗を手で拭きながらあえいだ。「実を言うと何がなんだかさっぱりです。ホームズさん、ちょっと、もったいをつけすぎではないですか?」
「そうですね、大佐。そろそろすべてが判明しますので、みんなで馬を見に行きましょう。さあ、あそこだ」ホームズは、オーナーか同伴者だけに立ち入りが許されている計量の囲いに向かいながら言った。「アルコールで、顔と足をちょっと拭けば、まぎれもなくシルバー・ブレイズだとわかるでしょう」
「これは、たまげた!」
「私はあるペテン師がこの馬を持っているのを見つけ、勝手ながら返してもらったままの状態で走らせました」
「ホームズさん、驚きました。馬は絶好調のようです。こんなに調子が良かったことはありません。ホームズさんの能力を疑ったりして本当に申し訳ない。ホームズさんは見事な手際で馬を取り返してくださいました。これでジョン・ストレイカーの殺人犯を捕まえれば、一件落着なのですが」
「もう捕まえました」ホームズは静かに言った。
ロス大佐と私は驚いてホームズを見つめた。「捕まえた!それでは犯人はどこに?」
「ここにいます」
「ここに!どこですか?」
「今、僕のとなりにいます」
ロス大佐は怒りで真っ赤になった。「ホームズさんに恩義があるのは、よくわかっていますが」ロス大佐は言った。「それは失敬な冗談か侮辱です」
シャーロックホームズは笑った。「大佐が共犯者だとは思っていませんよ」ホームズは言った。「真の殺人犯はすぐ後ろに立っています」ホームズはサラブレッドに歩み寄り、ツヤツヤした馬の首に手を当てた。
「馬が!」ロス大佐と私は同時に叫んだ。
「そうです、馬です。ただ、これは正当防衛で、ジョン・ストレイカーは、あなたが信頼を置けるような人物ではまったくなかったと、僕が弁護すれば、罪も軽くなるでしょう。しかしベルが鳴りましたね。次のレースでちょっと勝ちたいので、詳しい説明は、もっと時間の余裕のあるときにしましょう」
その夜、ロンドンに帰る際、寝台車の一角を確保して、ホームズから月曜の夜ダートムーアの調教厩舎で起きた出来事と、それを解明した手法について話を聞いたので、私だけではなく、ロス大佐も、この車中はあっという間に過ぎただろうと思う。
「実は」ホームズは言った。「僕が新聞の情報から構築していた理論は、まったくの見当違いだった。もちろん、新聞にも手掛かりはあったのだが、枝葉のような情報に、真実が隠されていたからだ。デヴォンシャーに来たとき、真犯人は、まずフィッツロイ・シンプソンだとは思っていたが、彼の犯行だと断定するには、どう見ても証拠が不十分だった。ストレイカーの家に馬車が停まった瞬間、やっとマトンのカレー煮が決定的に重要だと気づいた。皆さんが馬車を降りた後、僕が中でぼんやりしていたのを覚えているでしょうか。心の中で、こんなに明白な手掛かりを、なぜ見逃すことができたのかと驚いていたのです」
「すみません」ロス大佐が言った。「それを聞いてもどこが重要なのか、わかりませんが」
「これこそ、最初につかんだ推理の起点だった。阿片粉末には味がある。不愉快ではなくとも、特徴的な味だ。もし普通の食事に混ぜれば、口にした人間は必ずそれに気づき、食べ進まないだろう。間違いなく、カレーは阿片の味をごまかす手段だ。しかしフィッツロイ・シンプソンという部外者が、あの夜、ストレイカー家の献立をカレー味にできるとは、とても想定できない。たまたま味をごまかせる料理が出た夜に、これもたまたま阿片粉末を持ってやって来たというのは、まず考えられない偶然だ。したがって、シンプソンは容疑者から除外できる。それに代わり、夕食の献立をマトンのカレー煮にできたストレイカー夫妻が浮上する。同じ料理を食べた他の人間に異常がなかったので、阿片を入れたのは、厩舎番用に取り分けた後になる。ではメイドに見られることなく料理に近づけたのは、夫か妻か?」
「この問題を解決するために、犬が静かだったことが重大な意味を持つことがわかっていた。ひとつの正しい推論は自然に、新たな成果につながる。シンプソンの事件で、犬はずっと厩舎の中にいたことがわかった。ところが、人が入って馬を連れ出しているのに、吠えて屋根裏で寝ている馬丁が目を覚ますことはなかった。明らかに、夜中に訪れたのは犬がよく知る人物だったはずだ」
「僕はもう確信していた。確信が言い過ぎなら、ほぼ間違いない、と思っていた。真夜中に厩舎へ行き、シルバー・ブレイズを連れ出したのは、ジョン・ストレイカーだと。何のために?明らかに、よからぬ目的だ。そうでなければ、なぜ厩舎番を薬で眠らす必要があるだろうか?しかし、何をするつもりだったのかが、わからなかった。調教師が大金を得るために、代理人経由で対抗馬に賭け、不正な方法で自分の馬を負けさせた事件は過去にも例がある。騎手がグルになったこともあるが、もっと確実で手の込んだ策略もあった。今回の手口は何か?それを突き止める手掛かりは、ストレイカーのポケットにあるのではないかと考えた」
「そして、予想は的中した。死んだ男が握っていた奇妙なナイフは印象的だが、まともな人間が、あのナイフを武器として選ぶことは絶対にない。あれは、ワトソン博士が言う通り、非常に繊細な外科手術用で、あの夜、ナイフは最も繊細な手術に使われるはずだった。ロス大佐、競馬界で経験豊富なあなたなら、馬の腿の裏側の腱にごく小さな傷をつける際、皮下で行えばまったく跡が残らないようにすることができるのをご存知でしょう。手術を受けた馬は軽く足を引きずるようになるが、運動の疲れか軽いリューマチのように見え、不正行為だとは気づかれない」
「悪党!裏切り者め!」ロス大佐は叫んだ。
「ジョン・ストレイカーが馬を荒野に連れ出す必要があった理由は明らかだ。健康な動物がナイフで切られた痛みを感じれば、絶対に暴れて、どんなに熟睡している人間でも目を覚ます。だから、何としても戸外で執刀しなければならない」
「人を見る目がなかった!」ロス大佐は叫んだ。「それでロウソクが必要になってマッチを擦ったのか」
「まさしく、その通り。しかしストレイカーの所持品を調査中、幸運にも犯罪の手段だけでなく、動機も発見できた。社会経験豊富な大佐ならご存知の通り、他人の請求書を持ち歩く人はいない。普通の人間は、自分の支払いだけで精一杯だ。そこで、すぐにストレイカーは別の家庭を持つ、二重生活者だという結論に達した。請求書の品目から、事件の陰には金づかいの荒い女がいたとわかる。大佐がどれだけ気前よく給料を支払っていたとしても、彼が妻に20ギニーの外出着を買ってやれるとは考えられない。さりげなくストレイカー夫人にあのドレスについて質問すると、別の女の服だとわかったので、衣料店の住所をメモし、ストレイカーの写真を持ってその店に行けば、簡単にダービシャーという男の謎を解決できると考えた」
「ここから先の出来事はすべて明白だ。ストレイカーは馬を窪地に連れて行った。そこなら明かりをつけても誰にも見られない。シンプソンは逃げるときにネクタイを落とし、ストレイカーがそれを拾っていた。何か考えがあってのことだろう。もしかすると、馬の足を固定するのに使えると思ったのかもしれない。窪地に行くと、ストレイカーは馬の後ろに回ってマッチを擦った。しかし馬は、突然の光に恐怖を感じ、神秘的な動物の本能によって、危害が加えられそうだと察知して先制攻撃したところ、蹄鉄が額を直撃した。雨が降る中、ストレイカーはこまかい作業をするために、あらかじめコートを脱いでいた。そのため、倒れるときに自分の腿をナイフで切り裂いてしまった。わかりにくいところはありませんか?」
「素晴らしい!」ロス大佐は叫んだ。「素晴らしい!その場にいらっしゃったみたいだ」
「最後の賭けは、本当に大穴狙いだった。僕はストレイカーのような抜け目のない男が、ぶっつけ本番でこんな繊細な手術をするだろうか、ということに気づいた。練習台になりそうなものは何か?羊に目がとまった。そして質問すると、なんと、その想定が裏づけられた」
「ロンドンに戻って衣料店を訪ね、店主にストレイカーの写真を見せると、高級服に目がない衣装道楽の妻がいるダービシャーという上得意だと答えた。この女がストレイカーを借金まみれにして、今回の不幸な計画に追い込んだとみて、間違いない」
「すべて説明していただけましたが、ひとつだけまだです」ロス大佐は叫んだ。「馬はどこにいたんですか?」
「ああ、逃げてから、ご近所の方が世話をしていました。これは目くじらを立てるようなことではないでしょう。おや、もうクラッパム・ジャンクションか。ビクトリア駅まで10分もないな。大佐、ベーカー街で一服するおつもりがありましたら、それ以外にききたいことがあれば喜んでお話ししますよ」